障害者虐待防止法が平成24年に施行されましたが、今なお凄惨な虐待行為は後を絶ちません。
虐待は必ずしも悪意から起こるわけではありません。介護や支援に疲れ果て、気づかないうちに行為が虐待に該当してしまうケースもあります。また、虐待を受けている障がい者本人が「自分は虐待されている」と認識していないことも多いです。「これって虐待では?」と思うような場面に遭遇することもあり得ます。
そこで今回は、障がい者虐待の5つの類型について具体例をあげながら解説します。障がい者虐待について理解を深め、早期発見につなげましょう。
※固有名詞、法律から引用している場合などは「障害」と表記しています。
定義
障がい者虐待とはどういったものかを説明するために、少し法律を紐解いてみましょう。
障がい者虐待は、平成24年10月1日に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)によって定義づけされています。
「障害者」とは
障害者虐待防止法第2条第1項および障害者基本法第2条第1号によれば、「障害者」とは、
身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁(日常生活を営む上で障壁となる事物、制度、慣行、観念など)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの
とされています。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人はもちろんですが、発達障がいや自立支援医療の利用者など手帳を持っていない人も含めます。また、18歳未満の方を含みます。
「障害者虐待」とは
「障害者虐待」についても法律で定義づけされています。それによると、障がい者虐待は①養護者による障がい者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待、③使用者による障がい者虐待のことを指します。
養護者…障がい者の身辺の世話や身体介助、金銭の管理等を行っている障害者の家族、親族、同居人等
障害者福祉施設従事者等…障がい者福祉施設の従事者や障害福祉サービスを提供する事業者
使用者…障がい者を雇用する事業主又は事業の経営担当者
障がい者虐待の5つの類型

では、どんな行為が虐待に該当するのでしょうか。
先ほど障がい者虐待の定義を見ていただきましたが、いずれの場合でも下記の5つに分類されています。
- 身体的虐待
- 性的虐待
- 心理的虐待
- ネグレクト(放棄・放置)
- 経済的虐待
一つずつ見ていきましょう。
身体的虐待
法律の中では「身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」と定義されています。
身体に外傷が生じる暴行とは、叩いたり蹴ったりという暴力行為の他にも、
- 物を投げつける
- 腕を強く引っ張る
- 熱湯や冷水をかける
- 辛いものや食べられないものを食べさせる
といったことが該当します。
そしてもう一つ気を付けなければならないのが身体拘束です。
身体拘束とは道具や薬剤を用いて身体的自由を奪うことです。例示すると、
- 障がい者を椅子やベッドに縛り付ける
- 自分の意志で開けることができない部屋に閉じ込める
- 障がい者の手にミトン手袋をはめたり、つなぎを着せる
- 薬を与えて行動を制限する
といったような行為が身体拘束にあたります。
ここで気になるのが、たとえば強度行動障がいの人のような自傷他害が見られる障がい者に対してはどうかということです。
- 自分の体をたたく、壁に頭をぶつける
- 傷を搔きむしる
- パニックになると大声をあげたり、周囲の人を傷つけたりする
- 食べられないものを口に入れる
- 道路で危険な飛び出しをする
- 他人をたたく、押す
このように自傷他害の行動が確認され、本人や周りの人を守るためにも身体拘束もやむを得ないのでは?と思われるかもしれません。しかし、身体拘束には「正当な理由」が必要となりますので要注意です。
正当な理由とは①切迫性、②非代替性、③一時性の3つです。
①切迫性…障がい者などの生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が高い状況であるかどうか
②非代替性…身体拘束その他の行動制限をおこなう以外に代替できる手段がない状況であるかどうか
③一時性…身体拘束、そのほかの制限が一時的で短時間なものであるかどうか
この3つの要件すべてに当てはまる場合にのみ、身体拘束はやむを得ないとされています。
障がい者支援施設などで身体拘束が検討される場合、個別支援会議などにおいて組織として慎重に検討、決定される必要があり、その結果身体拘束が必要と判断される場合には個別支援計画に身体拘束の様態及び時間、緊急やむを得ない理由を記載しなければなりません。
その上で適宜障がい者本人や家族に十分に説明し、了解を得ることが必要です。
身体拘束を行った場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由などの必要な事項を記録しなければなりません。
性的虐待
法律の中では「わいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること」と定義されています。具体的には次のようなことが該当します。
- キスをする
- 性行為を強要する
- わいせつな言葉を言う、わいせつな図画を見せる
- 裸にする、写真を撮る
- 人前で排泄させたりおむつ交換をしたりする
心理的虐待
法律では「著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」と定義されています。具体的には次のようなことが該当します。
- 威嚇的な発言や態度をとる(怒鳴る、罵る、脅すなど)
- 侮辱的な発言や態度をとる(失敗を嘲笑する、「ばか」「あほ」などと言う、子ども扱いするなど)
- 無視や尊厳の否定(話しかけを無視する、本人や家族の悪口を言いふらすなど)
- 自立心を低下させる行為(本人の意思を無視する、意思や状態を無視して介助するなど)
- 交換条件の提示(「これができたら外出させてあげる」と言うなど)
- 心理的に孤立させる(訴えを無視する、家族と面会させない、仲間はずれにするなど)
ネグレクト(放棄・放置)
法律では「障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等、養護を著しく怠ること」と定義されています。具体的には次のようなことが該当します。
- 食事や水を与えない
- 汚れた服を着させ続ける
- 入浴や排せつなど必要な介助をしない
- ゴミが放置されているなど劣悪な衛生状態で生活させる
- 病気になっても治療を受けさせない
- 必要な福祉サービスを受けさせない
- 話しかけや訴えに対応しない
- 同居人による身体的虐待や心理的虐待を放置する
ネグレクトは養護者や事業者、使用者が放棄、放置するパターンだけではありません。障がい者の中には、病状(たとえばうつ状態)の影響で意欲が低下し、食事をとらない、体調が悪くても病院に行かない、ゴミを放置するなどの状態に陥ることもあります。これを「セルフネグレクト」(自己放任)と言います。
セルフネグレクトは障がい者虐待に定義されていませんが、支援が必要な状態である可能性が高いため対応が必要となります。
経済的虐待
法律では「障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること」と定義されています。具体的には次のようなことが該当します。
- 本人に無断で財産を処分、売却する
- 年金や賃金を管理して渡さない、無断で使用する
- 寄付や贈与を強要する
- 立場を利用して「お金を貸してほしい」と頼み借りる
虐待を受けたとき、見つけたとき

自分が虐待を受けたときや虐待を発見した時は、市町村役場の福祉事務所に通報しましょう。
特に虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合は速やかに通報しなければならないことが、法律に謳われています。
虐待は、本人や行為者の自覚の有無は問いません。客観的に見て障がい者の人権が侵害されていると判断できる場合には、対処しなければなりません。通報者の情報は厳重に守られます。
通報を受けた機関は調査を行い、虐待が確認された場合は被害者を安全な環境に避難させるなどの緊急対応が行われます。加害者には必要な支援や指導、再発防止のためのカウンセリング等のサポートが行われます。
まとめ
障がい者虐待の5つの類型を見てきましたが、いかがでしたでしょうか?もう一度、確認しましょう。
- 身体的虐待
- 性的虐待
- 心理的虐待
- ネグレクト(放棄・放置)
- 経済的虐待
これらの虐待は、身体に残る傷だけでなく心にも深刻な影響を与え、被害者の生活の質を大きく低下させます。
特に障がい者の場合は自ら声を上げることが難しく、虐待が長期間にわたって続いてしまうことが多いのが現状です。もし「これって虐待かもしれない」と思ったら、ためらわず専門機関に相談してください。間違いや思い込みを心配する必要はありません。
障がい者に関わるすべての人に、虐待をしない・させない、そして早期発見・早期対応を期待します。

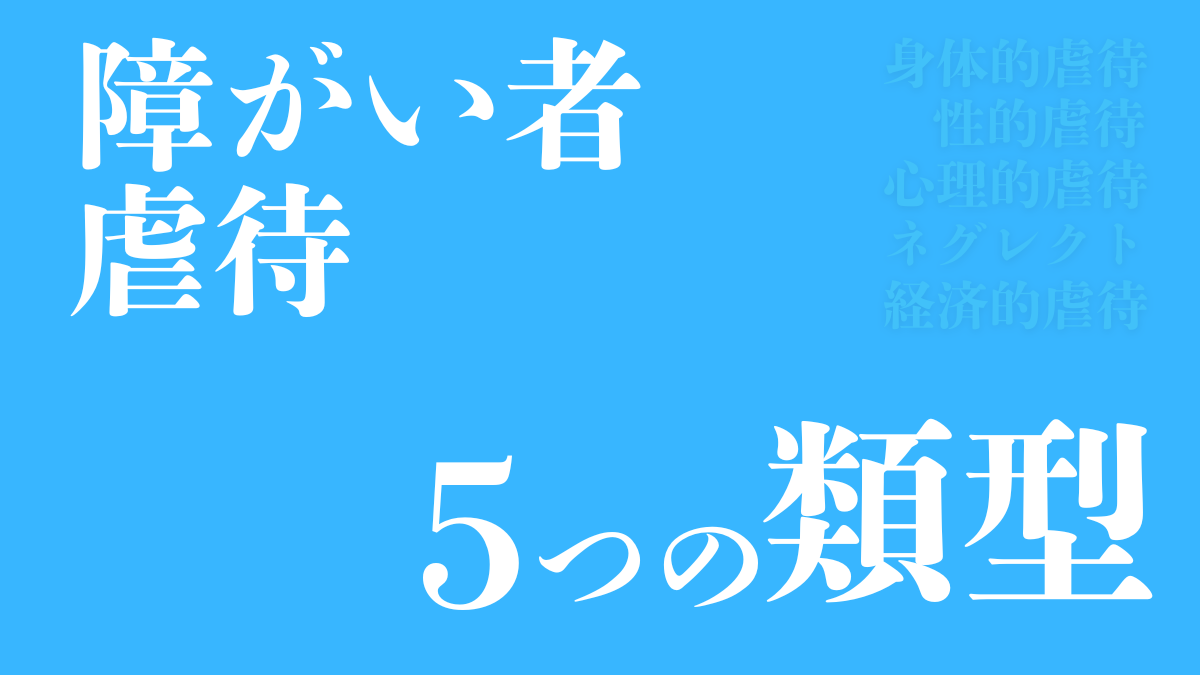


コメント